「生命を生みだす母親は 生命を育て 生命を守ることをのぞみます」をスローガンに、日本母親大会は毎年欠かさず開かれ、2004年には50回を数えるまでになった。さらに各都道府県から地域別市町村別の集会までふくめると、毎年春から秋にかけての「母親」の集いはおびただしい数にのぼるだろう。ところで母親運動 のはじまりは、1955年スイスのローザンヌで開かれた世界母親大会であるが、その後「母親」の名をつけた女性の運動がつづいている国は、他に例がないという。最近では、女性を「母親=母性の持ち主」ととらえることへの批判や、「性の自己決定権(リプロダクティブ&ライツ)」や「子育ては男女共同の仕事」という立場と矛盾するのではないかという意見も出ている。では母親運動はもう「古く」なったのだろうか。
のはじまりは、1955年スイスのローザンヌで開かれた世界母親大会であるが、その後「母親」の名をつけた女性の運動がつづいている国は、他に例がないという。最近では、女性を「母親=母性の持ち主」ととらえることへの批判や、「性の自己決定権(リプロダクティブ&ライツ)」や「子育ては男女共同の仕事」という立場と矛盾するのではないかという意見も出ている。では母親運動はもう「古く」なったのだろうか。
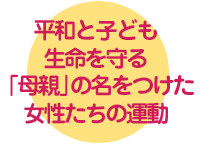 はっきりさせておきたいのは、母親運動は54年アメリカのビキニ水爆実験に反対し、平和を求める世論の中から生まれたことである。平塚らいてうが国際民主婦人連盟に原水爆禁止を願う日本女性の訴えを送ったのが、世界母親大会のきっかけであった。当時国際民婦連は、「恒久平和と子どもの幸福、婦人の解放」の三つを運動の柱としており、女性の権利とともに、ナチスドイツや日本軍国主義によって多くの子どもたちのいのちが奪われた事実をふまえて、戦争から「子どもを守る」ことを女性の要求としたものであった。日本の「母親」の立場はかつて無権利であったがゆえに戦争を阻止することができず、「軍国の母・妻」になってしまった女性たちの「二度と戦争を起こすな」という要求に支えられていた。
はっきりさせておきたいのは、母親運動は54年アメリカのビキニ水爆実験に反対し、平和を求める世論の中から生まれたことである。平塚らいてうが国際民主婦人連盟に原水爆禁止を願う日本女性の訴えを送ったのが、世界母親大会のきっかけであった。当時国際民婦連は、「恒久平和と子どもの幸福、婦人の解放」の三つを運動の柱としており、女性の権利とともに、ナチスドイツや日本軍国主義によって多くの子どもたちのいのちが奪われた事実をふまえて、戦争から「子どもを守る」ことを女性の要求としたものであった。日本の「母親」の立場はかつて無権利であったがゆえに戦争を阻止することができず、「軍国の母・妻」になってしまった女性たちの「二度と戦争を起こすな」という要求に支えられていた。
第一回の母親大会で、子どもを背負った母親の「涙の訴え」がマスコミに報道され、無力な女性がわが子を抱きしめるイメージが広がったが、これは今からみるとまさに「ジェンダー」的な見方である。遠く前近代の一揆や打ちこわしから近代の米騒動、戦後の食糧獲得闘争にいたるまで、女性は生活要求をかかげたたたかいにいつも「子連れ」で参加してきた。子どもの健やかな成長を、個々の家族のなかだけで考えずみんなで話しあおうということ自体、女性の社会参加の一歩だった。60年代の母親運動が小児マヒ防止の生ワクチンを、と交渉して厚生省(当時)を動かした事実は、わが子だけを守ろうという「母親」からの飛躍を意味していた。
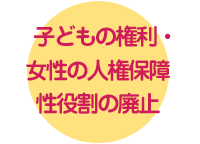 同時に母親運動50年の間に、女性をとりまく状況も変わり、女性の運動は国際的にも理論的にも深化してきている。60年代以降女性の社会進出がすすみ、差別賃金問題や年金・高齢者問題、公害からコメ問題、安保問題まで人間生活の根本にかかわる社会問題・政治問題がみなとりあげられるようになった。とくに最近注目されるのは、「母親」というだけでなく「自分らしく生きたい」という要求が広がっていることである。それは、「女性のわがまま」だろうか。そうではなく、いま女性が就職もできず、昇格もできず、夫は過労死するほど働かされて家事育児どころではないなかで「性役割」が再生産されている現実を「がまんできない」精神が育ってきたことのあかしではないだろうか。
同時に母親運動50年の間に、女性をとりまく状況も変わり、女性の運動は国際的にも理論的にも深化してきている。60年代以降女性の社会進出がすすみ、差別賃金問題や年金・高齢者問題、公害からコメ問題、安保問題まで人間生活の根本にかかわる社会問題・政治問題がみなとりあげられるようになった。とくに最近注目されるのは、「母親」というだけでなく「自分らしく生きたい」という要求が広がっていることである。それは、「女性のわがまま」だろうか。そうではなく、いま女性が就職もできず、昇格もできず、夫は過労死するほど働かされて家事育児どころではないなかで「性役割」が再生産されている現実を「がまんできない」精神が育ってきたことのあかしではないだろうか。
母親運動の中心にいた山家和子は「母親運動の原点は平和と子ども」と表現したが、それは女性が自己犠牲的に「母」になるのではなく、子どもの権利保障の担い手になることを意味している。国際的な女性運動の流れは、性役割の廃止を強く求めているが、同時に「女子差別撤廃条約」がいうとおり「あらゆる場合において子の利益は最初に考慮する」こともうたっているのである。これは「子どもの権利条約」と同じ文言である。
 いま、戦争で殺され、地雷で吹き飛ばされ、売られ、虐待される無数の子どもたちをほんとうに守るみちは、女性が自立した個人として人権を保障されることなしにありえないのではないか。母親運動が子ども=生命を守る運動として積み上げられてきたものをふまえて21世紀の新しい前進を期待したい。
いま、戦争で殺され、地雷で吹き飛ばされ、売られ、虐待される無数の子どもたちをほんとうに守るみちは、女性が自立した個人として人権を保障されることなしにありえないのではないか。母親運動が子ども=生命を守る運動として積み上げられてきたものをふまえて21世紀の新しい前進を期待したい。